1. 昔の秋の行事を振り返る
昔の秋には、自然の恵みを感謝する行事が多くありました。代表的なのは「十五夜(じゅうごや)」と呼ばれるお月見です。旧暦の8月15日にあたるこの日は、満月を眺めながら収穫に感謝する習慣がありました。すすきを飾ったり、お団子や果物をお供えしたりするのが特徴です。利用者さんにとっては懐かしい思い出になることも多いでしょう。 また、「重陽(ちょうよう)の節句」は9月9日に行われ、菊の花を愛でて長寿を祈る行事です。菊は薬草としての役割もあり、健康への願いが込められていました。こうした行事の話をすることで、利用者さんの記憶を刺激し、心が和む時間を作れます。 これらの秋の伝統行事は、季節感を感じながら昔の暮らしを思い出すきっかけになります。介護や看護の現場でぜひ話題にしてみてください。2. 秋の旬の食べ物を話題にする
秋は美味しい食べ物がたくさん出回る季節です。栗やさつまいも、さんま、柿などは代表的な秋の味覚で、昔から親しまれてきました。栗は甘みがあり、栗ご飯やお菓子に使われます。さつまいもは甘くて栄養豊富で、体を温める効果もあります。 さんまは脂がのった魚で、良質なタンパク質やDHA(脳の働きを助ける脂肪酸)が豊富です。柿はビタミンCや食物繊維を含み、健康維持に役立ちます。これらの食べ物について話すと、自然と健康や昔の食生活の話に繋がりやすく、会話が広がります。 利用者さんに「昔はどんな風に食べていたか」「家族でどんな料理を作ったか」と尋ねると、楽しい思い出話が聞けるでしょう。3. 介護・看護の現場で活かす昔の秋の話題
利用者さんとのコミュニケーションは信頼関係を築く大切な時間です。秋の行事や旬の食べ物の話題は、懐かしさを呼び起こし、会話を弾ませます。話を聞く姿勢を大切にし、相手の思い出を引き出すことがポイントです。 また、食べ物の栄養価について軽く触れると、健康への関心も高まります。たとえば「さんまには脳に良い脂肪酸が多いんですよ」と伝えると、興味を持ってもらえます。 忙しい現場でも、こうした小さな会話を積み重ねることで、利用者さんの心が安らぎ、笑顔につながります。ぜひ積極的に取り入れてみてください。まとめ
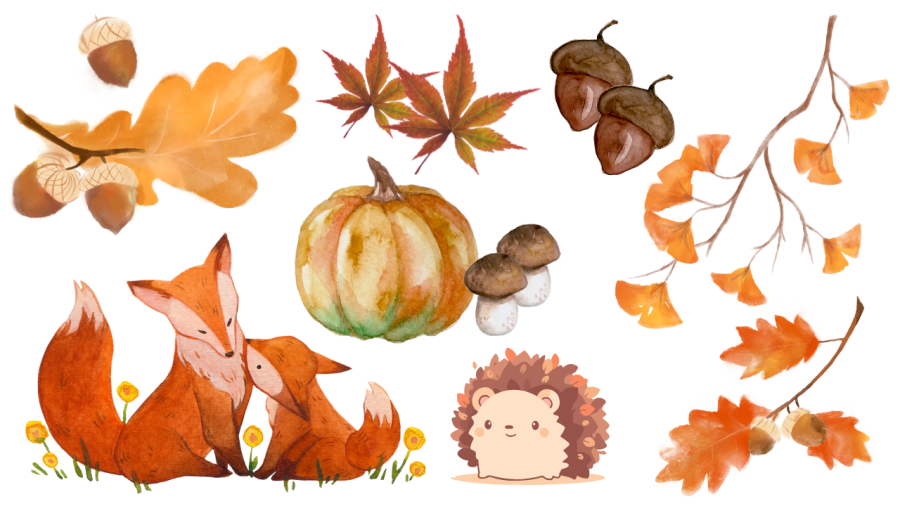 昔の秋の行事や旬の食べ物の話題は、利用者さんとの会話を豊かにし、心の交流を深めるきっかけになります。季節感を感じながら、昔の思い出や健康の話を取り入れて、信頼関係を築いていきましょう。
昔の秋の行事や旬の食べ物の話題は、利用者さんとの会話を豊かにし、心の交流を深めるきっかけになります。季節感を感じながら、昔の思い出や健康の話を取り入れて、信頼関係を築いていきましょう。
▼LINEで簡単登録・相談も受付中! LINE公式アカウントに登録する

