~季節の変わり目を健康に乗り切るために知っておきたいこと~
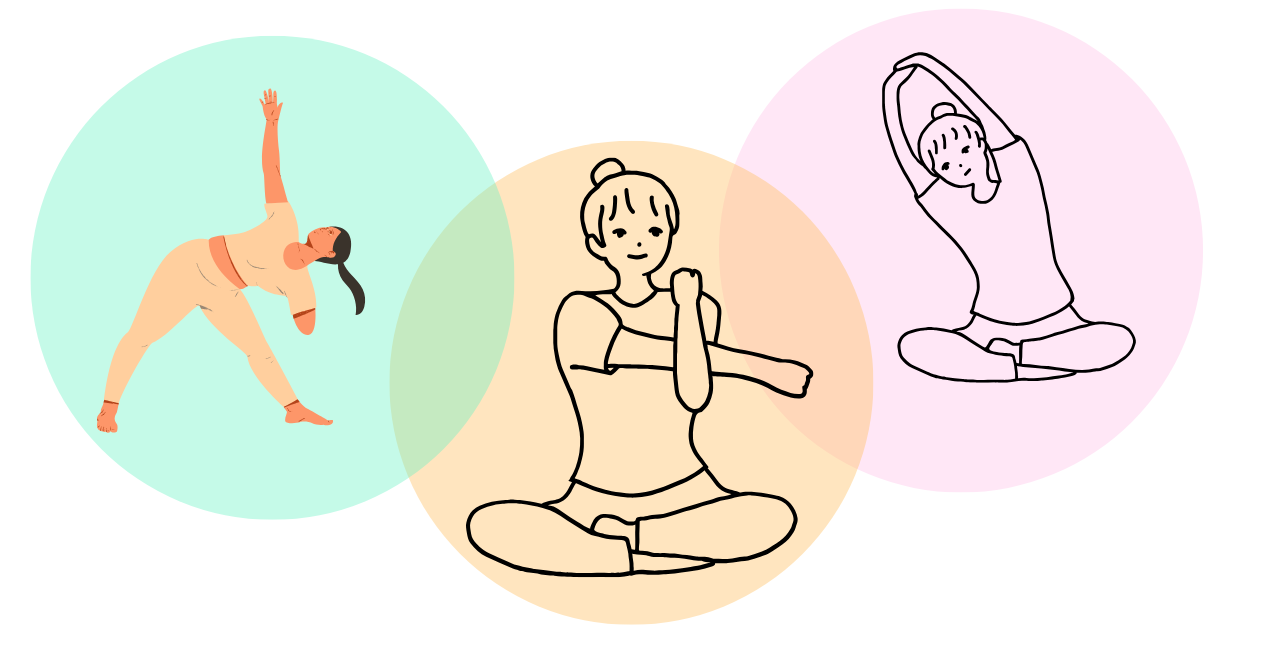
10月は秋が深まり、朝晩の冷え込みと日中の暖かさの差が大きくなる季節です。この「寒暖差」が体に負担をかけ、体調を崩しやすくなる時期でもあります。介護・看護の仕事は体力を使ううえ、体調管理が特に大切です。今回は、10月に増える体調トラブルの原因と予防のポイントについてわかりやすく解説します。
1. 10月に多い体調トラブルとは?
寒暖差が大きい10月に特に注意したい体調トラブルは以下の通りです。
- 風邪やインフルエンザ:寒暖差で体の免疫力が低下し、ウイルスに感染しやすくなります。
- 頭痛やめまい:急な気温変化で自律神経が乱れ、血管が収縮・拡張を繰り返すことで起こりやすくなります。
- 疲労感や倦怠感:体が温度変化に対応するためにエネルギーを使い、疲れやすくなります。
- アレルギー症状の悪化:秋は花粉やほこりが増え、鼻炎や咳がひどくなることがあります。
2. 寒暖差が体に与える影響とは?
寒暖差が大きいと、体は自律神経というシステムを使って体温調節を行います。この自律神経は、心拍数や血圧、呼吸、消化など無意識に体をコントロールしていますが、寒暖差が激しいとバランスが乱れてしまいます。
乱れると、血管の収縮・拡張がスムーズにできなくなり、頭痛やめまい、肩こりなどの症状が出やすくなります。また、免疫機能も低下し、風邪や感染症にかかりやすくなってしまうのです。 特に介護・看護の現場では身体的負担が大きいため、自律神経の乱れが体調不良に直結しやすい環境と言えます。3. 10月の寒暖差によるトラブルを防ぐ日常の工夫
寒暖差の影響を減らすために、普段の生活でできる工夫をご紹介します。
- 服装の調節をこまめに:重ね着や脱ぎ着しやすい服を選び、外出時や職場での温度変化に対応しましょう。
- 室内の温度管理:エアコンや暖房器具を活用して室温を20~22度前後に保つと体への負担が減ります。
- こまめな水分補給:気温差で体内の水分バランスが崩れやすいので、意識的に水分を取りましょう。温かい飲み物がおすすめです。
- 十分な睡眠と休息:自律神経のバランスを整えるためには、質の良い睡眠が欠かせません。規則正しい生活リズムを心がけましょう。
- バランスの良い食事:ビタミンやミネラルを豊富に含む食事は免疫力アップにつながります。旬の野菜や果物を積極的に取り入れてください。
まとめ
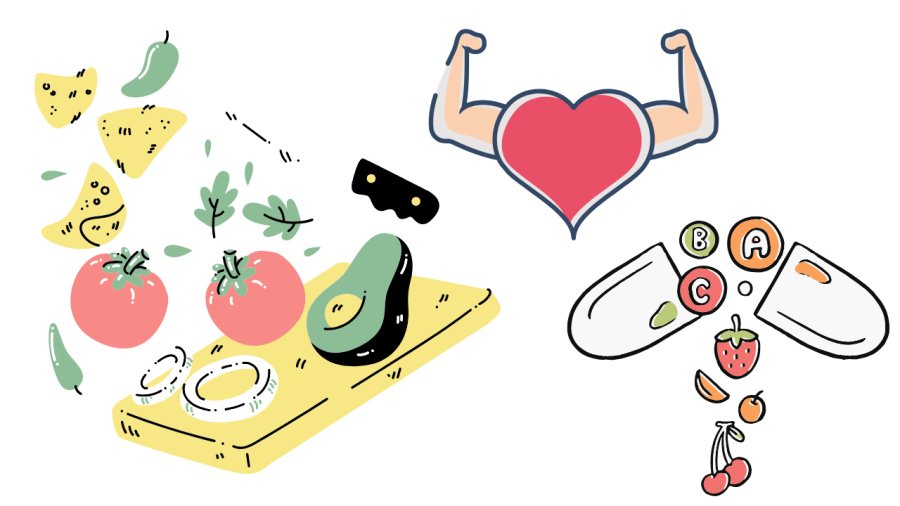
10月は寒暖差が大きく、体調トラブルが増えやすい季節です。
- 風邪や頭痛、疲労感などの症状に注意する
- 寒暖差が自律神経に与える影響を理解する
- 服装や室温管理、水分補給、睡眠、食事で予防を心がける
▼LINEで簡単登録・相談も受付中! LINE公式アカウントに登録する
